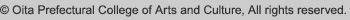生成AIのルール
本学における生成AIに関するルールについて
Chat GPTをはじめとする生成AI(Generative AI)が数多く開発され、我々の生活にも広く浸透するようになってきました。これらの生成AIを使用することで、様々な問いかけに対して瞬時に回答を得たり、新しいアイデアを出したり、作詞・作曲・デザイン・プロ グラミング・翻訳などが容易にできるようになりました。
今後、生成AIがさらに社会に普及することは間違いなく、これにより人手不足の解消、生産性の向上、新たな価値創造などが期待できるようになるものと考えられます。またこの技術の進展は、我々の働き方、生活様式、さらには社会や産業の構造を一変させる可能性すら存在しています。
本学では2023年5月に「生成系AI(人工知能)の利用に関する注意喚起」を公表して、これに則した運用を図ってきましたが近年、生成AIの利点と課題がより明らかになるととともに、国際的なルール作りも始まりだしていることから、本学では生成AIの利用に関して以下のようにルールを新たに設けることとします。
・本学では、生成AIの利用について一律に禁止はしません。大学の授業における生成AIの利活用の可否については、それぞれ科目の担当教員の指示に従うようにしてください。 なお担当教員が「生成AIを使うことを禁じます」と指示しているにもかかわらず、生成AIを使って出力内容をそのままレポートや課題として提出した場合は、カンニングや剽窃 (他人の作品などを盗んで自分のものとして発表すること)等の不正行為とみなし、学生懲戒規定に則り処分を行うことがあります。
・生成AIは、入力された内容を学習・蓄積する仕組みとなっているため、個人情報やプラ イバシーに関わるようなものを入力すると、その情報が外部に流出・漏洩することが強く懸念されます。そのため、このような個人情報を含む内容を入力する行為は、厳に慎んでください。また生成された情報のなかに個人情報が含まれる場合は、生成物をみだりに利用するようなことはしないでください。
・生成AIによって作りだされた内容は、必ずしも正しいものであるとは限らないため、内容が正しいものであるのか否かを、しっかりと事実確認することが求められます。また生成された情報は最新のものでないこともあるため、しっかりと一次情報を自ら調べ、確認してください。 ・生成AI が作り出す文章や画像などに、他人の著作物との類似性・依拠性が認められる場合は、著作権の侵害に該当する場合があります。よって生成AIを利用する場合は、著作権等の保護されるべき権利を遵守するようにしてください。
・レポート、論文、作品などの作成で担当教員が生成AIの使用を認めた場合でも、これを使用して作成した場合は、生成AIを利用して作成したこと、またはAIから引用している ことを必ず明記してください。その場合は、出力内容を引用・利用した箇所を明示し、使用した生成AIの種類(例:Chat GPT)、バージョン(例:GPT-3.5)を明記してください。 最後に、大学における学びとは、学生自らが主体的に考え、物事の真理・真相を明らかにし、且つ社会における諸課題を解決する能力を磨くことにあります。また技芸に⾧けた能力を身に付け、社会に貢献することにあります。よって生成AIはあくまでもツールであ るということを強く認識し、これらを正しく使いながら学問に取り組んでください。また メディアリテラシーをしっかりと理解しつつ、上記ルールに準じて利用するようにしてく ださい。
以上










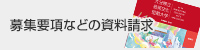
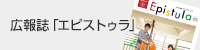
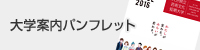
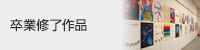
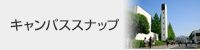
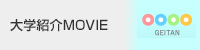
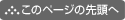
 RSS
RSS